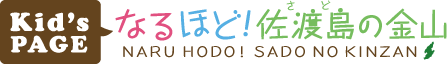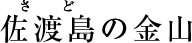-
地中
何メートルまで
掘ったの?
クリックして
正解を
見る!
大立竪坑は352m、高任立坑は667mまで採掘しました。
-
坑道の
長さはどのくらい?
クリックして
正解を
見る!
山の
至る
所で
縦横無尽に
掘られましたが、
全ての
長さを
合計すると400kmで、
佐渡から
東京までの
距離に
匹敵します。
-
佐渡で
産出した
銀と
銅はどのように
使われたの?
クリックして
正解を
見る!
銀は、
小判に
混ぜて
金との
合金として
使用しました。また、
銀そのものを
重さで
測り、お
金として
使用しました。
銅は「
仏像」や「
貨幣(コイン)」として
使用されました。
-
佐渡での
金と
銀の
産出量はどれくらい?
クリックして
正解を
見る!
金は
江戸時代に41t、
明治以降には37tと、
計78t
産出されました。
銀は
休山までの
間に2,330t、
銅は5,410t
産出されました。
-
江戸時代の鉱山の作業では、どのような危険があったの?
クリックして
正解を
見る!
一般的に坑道を深く掘り続けると、落盤、転落、呼吸器の病気などの危険があります。佐渡の岩盤は硬かったため、落盤事故は少なかったと考えられています。
-
鉱山では
子供も
働いていたの?
クリックして
正解を
見る!
坑内でいろいろな仕事を手伝う15歳以下の子供が働いていました。鉱石を運搬したり、荷物を上げたり、岩盤が崩れないように補強作業の手伝いもしました。また、鉱山で使う道具や、暗い坑道内で使う照明用の油を供給したりもしました。
-
鉱山で
働く
人は
何人くらいいたの?
クリックして
正解を
見る!
最盛期(
江戸時代初期)の
相川の
人口は
約5
万人で、そのほとんどが
鉱山関係の
労働に
従事していたと
考えられています。
食糧確保のため、
新田開発も
盛んに行われました。
-
佐渡の
鉱山にはまだ
金があるの?
クリックして
正解を
見る!
まだ金鉱脈は残っていますが、利益が出ないので採掘していません。
-
金山は
誰でも
勝手に
掘ってもよいの?
クリックして
正解を
見る!
文化財保護法で国の史跡として保護されているため、勝手に掘ってはいけないことになっています。
-
西三川では
今でも
砂金は
採れるの?
クリックして
正解を
見る!
僅かですが砂金は採れます。佐渡西三川ゴールドパークは有料の施設で、砂金採り体験にチャレンジすることができます。
-
江戸時代の金山では、どのような勤務体制だったの?
クリックして
正解を
見る!
鉱石を掘る鉱夫は、2人一組で4時間ずつ(計8時間)採掘を行いました。江戸後期になると鉱夫の数が不足し、長時間労働することが多くなりました。また、湧水を坑道の外に運ぶ水替人足の労働時間は、隔日交代の一昼夜勤務と大変なものでした。
-
坑道は
現在どのような
使い
方をしているの?
クリックして
正解を
見る!
坑道の
一部が
整備され、
観光用に
公開されています。
坑道内は常に10℃程度であることから、今では酒や食品を熟成させる倉庫としても利用されています。「南沢疎水道」は一般公開されていませんが、鉱山の湧水の排水路として現在も使用されています。
-
江戸時代を
通して
幕府から
派遣された
奉行は
何人くらいいたの?また、
奉行所には
何人くらいが
働いていたの?
クリックして
正解を
見る!
奉行は
幕末までに102
人に
達しました。また、
奉行所には200~280
人が
働いていたと
考えられています。
-
「水上輪」や「
唐箕」はどのように使用されたの?
クリックして
正解を
見る!
「水上輪」は地下水を地上に汲み上げる装置で、大阪の技術者である水学宗甫が造ったと言われています。その技術を水学宗甫に伝えたのは、キリスト教の宣教師であると推定されます。「唐箕」は風を起こす装置で、佐渡の金山では坑内の換気に使われていました。元禄(1688~1704年)頃からは、農作業で使用されるようになりました。
-
相川金銀山は
誰が
発見したの?
クリックして
正解を
見る!
相川金銀山は、
慶長6
年(1601
年)7
月、
鶴子銀山にいた3
人の
山師、
渡辺儀兵衛、
三浦治兵衛、
渡辺彌次右衛門が
発見したという
言い
伝えが
史料に
残っています。このときの
話は、
新潟県と佐渡市が作成した紙芝居「こがねの
山―
佐渡
相川金銀山発見伝―」で
紹介されています。この
紙芝居は、
市町村図書館や
県文化課で
貸し出しています。
-
坑道の
中で
使っていた
照明用の
油は?
クリックして
正解を
見る!
初めの
頃は
菜種油を
使っていましたが、
高価なため
魚油を使うようになっていきました。
しかし、
煙と
臭いが
出て
酸欠
等の
原因になるため、
再び菜種油を使うようになりました。