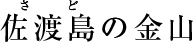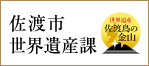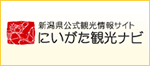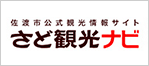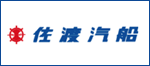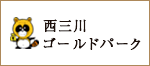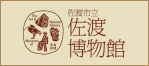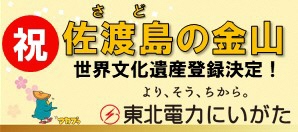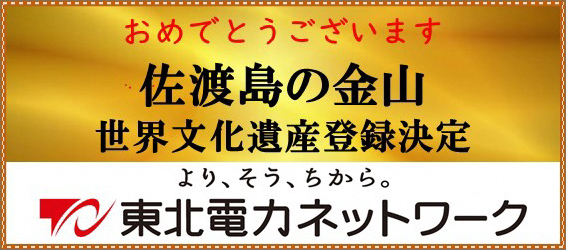「佐渡島の金山」には西三川砂金山、相川鶴子金銀山という2つのエリアがあり、
それぞれ異なる2つのタイプの鉱床の特性に合った技術が導入され、発展しました。


西三川砂金山の堆積砂金鉱床と砂金採掘法
佐渡最古の金の産地として知られる西三川砂金山は、地層の中に砂金が含まれる「堆積砂金鉱床」という特異な鉱床の鉱山です。砂金を得るためには、山の地層を掘り崩して不用な土砂を取り除く必要がありました。そのため、他の物質より重い金の性質と水の流れを利用して金を採掘・選鉱する「大流し」という以下のような独特な採掘手法が用いられました。
- 山裾に水路を設ける
- 水路に向かって山の地層を掘り崩す
- 水路で引いてきた水を堤に貯め、その水を一気に流すことで土砂を洗い流す
- 水路底に残る砂金を採取する
現地には、a.導水路跡(水源から水を引く)、b.堤跡(水を貯める)、c.配水路跡(採掘場に水を引く)、d.採掘場跡(山の地層を掘り崩す)、e.排水路跡(不要な土砂混じりの水を流し去る)など、大流しの一連の作業の仕組みを理解することができる遺構が残っています。

▲ 「大流し」砂金採掘法

▲ 最大の採掘場 現在の虎丸山
相川鶴子金銀山の鉱脈鉱床採掘の大規模化と技術改良
相川鶴子金銀山では、「鉱脈鉱床」という硬い岩盤を掘削して金銀を含む石(鉱石)を得ていました。鉱脈の規模や分布状況に応じて、鶴子から相川へと採掘が大規模化し、発展していったことがわかります。
-
 ▲ 初期の小規模な採掘(鶴子銀山)
▲ 初期の小規模な採掘(鶴子銀山) -
 ▲ 大規模な採掘(相川金銀山)
▲ 大規模な採掘(相川金銀山)
鶴子銀山では、露頭掘り、ひ追い掘り、坑道掘りといった採掘の跡が良好に残っており、採掘方法の変遷が見られます。
露頭掘り
地表に露出している鉱脈をまわりの土石ごと掘りとる。
ひ追い掘り
地表に露出している鉱脈を追いかけながら掘り進んでいく。
坑道掘り
山の中腹・山裾から水平方向に坑道(トンネル)を掘って、地中の鉱脈を採掘する。

相川金銀山は、鶴子銀山に比べて鉱脈が大規模で、地下深くまで及んでいたことから、採掘規模も大きく、長く深い坑道が掘られるようになりました。これに伴って生じた排水や換気の問題に対応するため、排水坑道(南沢疎水道)や換気機能を設けた坑道(大切山間歩)などの技術改良が進められました。

南沢疎水道(みなみざわそすいどう)
坑内の湧き水を排水するために5年間かけて手作業で掘られた排水用の坑道です。6か所から同時に掘り進める「迎え掘り」という工法が採用された全長約1kmの坑道は、誤差がほとんどなく貫通していることから、当時の測量技術の高さがうかがえます。

大切山間歩(おおぎりやままぶ)
金を採掘するための本坑道に並行して、もう一本換気用の坑道が掘られていることが特徴です。2本の坑道数か所を部分的に連結させることで、坑内の空気循環を良くする工夫がなされています。